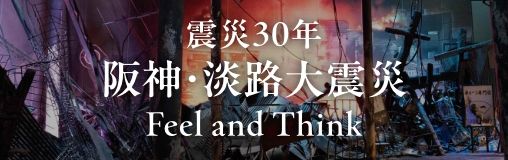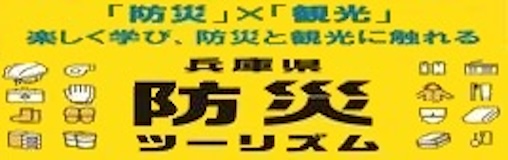テーマ
阪神・淡路大震災から20年
〜その経験を組織内でどう受け継ぐ〜
概要
阪神・淡路大震災から20年の節目を目前にして、メモリアルイベントや、特集記事、特別番組の準備が進められています。そうした節目のたびに私たちは、あの未曾有の災害を思い出すことはできますが、あの時困ったこと、あの時できなかったこと、次はこうすべきだと考えたことを、組織内で共有し、再確認できているでしょうか。
組織内には「震災を知らない世代」も増えてきています。他の地域での災害取材や応援派遣で、経験を積む機会はあったとしても、20年前に「この同じ場所で繰り広げられた災害の記憶」を受け継がない理由はありません。しかし、日々の業務の忙しさに埋もれ、なかなか上手な伝承ができていないという声が聞かれます。
そこで、第15回の研究会では、阪神・淡路大震災を経験した神戸市、神戸新聞社、三ツ星ベルトのご担当者様から話題提供をいただき、その後、参加者同士で意見交換を行いました。
開催日時
平成26年11月12日(水) 14:00~16:30
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 東館6階 第1・第2会議室
参加者
報道関係者、自治体職員等 計43人
次第
1. 議事
- 市長とともに 20年目の局長研修(神戸市危機管理室 総務担当係長 三川 博英 氏)
- 現場を仕切る中堅社員へ…修羅場の記憶(神戸新聞社会部デスク 編集委員 磯辺 康子 氏)
- 地域とともに災害を生き抜いた会社を、次世代へ(三ツ星ベルト 総務部長兼神戸事業所長 保井 剛太郎 氏)
2. 参加者同士の意見交換
参加した組織はいずれも、体系的な災害対応の伝承を行っておらず、先輩から後輩に、どんなことがあったかなどすら伝えられていないことが分かりました。スピーカーとなっていただいた組織、企業には、本社移転や市長の交代、20周年に向けてなど「語りを再開するきっかけ」があり、そのタイミングを上手に活用して「伝承の場」を作っていることが浮き彫りになりました。また、大変な経験をしたであろう人に対し、直接被災を経験していない者からは「聞きにくい雰囲気がある」という感想も聞こえ、災害対応を伝承するためには、時間の経過や経験の有無による「共通言語の差」を上手に埋める「場」づくりが必要であると感じました。進行役から「新人研修などの場を生かして、何ができて何ができなかったのかなどの経験談を伝える機会を、各組織で作りませんか」とよびかけ、研究会を締めくくりました。