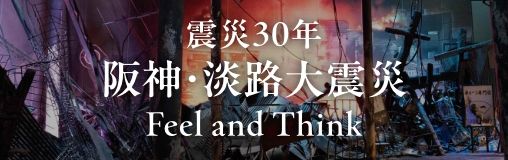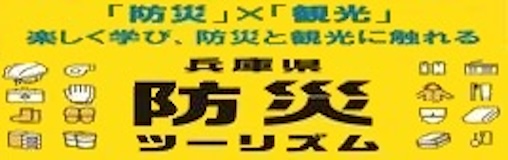社会の要請へ柔軟かつ機動的に対応するために、複数またはすべての研究員からなるチームが期間を限定して取り組む「特定研究プロジェクト」を設定しています。
特定研究プロジェクト
(令和7年度)
インクルーシブなミュージアムに向けた環境の検証
兵庫県教育委員会と神戸大学が実施するミュージアム・インクルージョン・プロジェクトにも参加しつつ、特別支援学校の支援対象となっている人々やその他の要支援者を念頭に、人と防災未来センターの展示におけるインクルーシブな在り方の検討・検証をします。それらの検討・検証を通じて、アクセシビリティと学習効果の向上を目指すことで、学習機会増加に貢献します。
ゲリラ豪雨に関する体験型ワークショップ手法の開発
気候変動の影響により、局地的豪雨の頻度・強度が増し、将来的にはさらに激甚化することが予想されていることから、ゲリラ豪雨に関する啓発・防災教育の推進の必要性はますます高まっています。子供たちにゲリラ豪雨の危険性について我がこととして理解を深めてもらうため、ゲリラ豪雨の特性である「局地性・突発性・予測困難性」を取り入れた、ゲーミング教材の開発に取り組みます。
災害に対する実効的な準備に関する研究
災害が頻発化、激甚化する我が国において、災害への備えについて、防災啓発等の取り組みが進められており、社会全体の防災への関心も高まっているとみられます。災害に対する最も初歩的な準備として、家庭における非常用持ち出し袋や備蓄、職場におけるBCP用備蓄等の対策が挙げられるが、その考え方について世間には様々な情報があふれています。本研究では、実効性の観点から、あるべき災害への準備を模索し、研究成果として発信することを目指します。
災害時孤立可能性地域における「緩い」広域連携圏の形成に関する研究
南海トラフ地震等の巨大災害では、孤立地域が同時に多数発生する懸念があります。特に県庁から遠方の地域では、「国→県→市町村」という従来の枠組みでは支援が行き届かない可能性があり、近隣市町村間での広域連携により災害初期を自立的に乗り切ることが求められます。本研究では、平時からの広域連携がみられる四国西南部や三遠南信地域などを例に、自治体や県といった圏域を超えた「緩い連携」がどのように生まれているのかを探り、災害時にどう機能しうるかを考察します。特に、県の本庁との関係で何を制度化する必要があるのかについて検討します。
巨大災害発生直後の行政職員の行動に関する研究
令和6年能登半島地震での当センターの現地支援での経験やつながりをもとに、能登半島地震発災直後の職員の行動について調査・分析し、大規模災害の発生時に、職員参集が難しいことも想定した初動対応について、どうあるべきかを検討します。