震災を語る 第2回
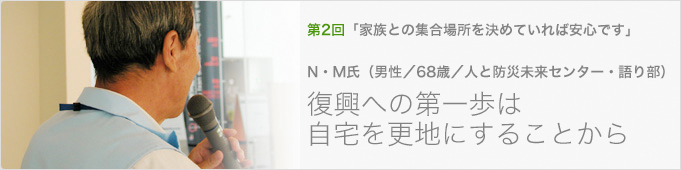
私の体験
自宅は倒壊、ただ運良く怪我一つなし
地震のあった当時、私は神戸市灘区で妻と2人、長屋のような2階建て木造住宅に住んでいました。
5時頃に起床する習慣があったので、地震のときは起きていました。そこで、8~10秒くらいで自宅が倒壊してしまうのを見たのです。屋根は南にずれて崩れるような形で倒壊、私自身、土壁に遮られて身動きができなくなりました。ですが、私と妻は井戸水で3日間(72時間)暮らしました。2人とも不思議と怪我もなく無事だったのです。
そこから、土壁の間から何とか這い上がるのに、4、50分かかりました。脱出したときはパジャマと裸足の姿。近所の人から靴をもらい、すぐさま手作業で近くのアパートにいる住民の救助にかかりました。救助した3世帯は、一人暮らしの女性に、2組の夫婦。この夫婦は、残念ながらどちらも奥さんが亡くなっていたのです。
徒歩5分の病院、小学校まで25分もかかる

この後、亡くなった方のご遺体やケガ人を運ぶため、避難所と病院へ向かうのですが、倒壊した家、倒れた電柱の間を歩くには、とても時間がかかるのです。徒歩5分の道のりに25~30分もかかってしまいました。すべての作業を終えるのに夕方までかかってしまったのです。
そしてこの日から小学校での避難所生活がはじまります。体育館で寝泊まりをしていたのですが、しばらくして授業を体育館で行うため、各教室へ移ることになりました。私は、4年1組。狭い教室に7人が寝泊まりする生活が続きます。もちろん、当時は会社員でしたので、会社へも小学校から通っていました。
復興への第一歩は自宅を更地にすることから
復興への第一歩は、3月2~9日にかけて、倒壊した自宅を更地にすることからでした。 続いて4月30日には、山陽電鉄荒井駅すぐの仮設住宅に移り住みます。さらに翌年1月15日には元の場所に新居が完成し、まる1年で元の場所に戻ってくることができました。これはかなり早い方だったのではないかと思います。
あの地震以来、近所の人はあちこちに移り住んでしまったため、今ではどこに転居してしまったのかわからない方がたくさんいます。私が元のところに戻ってきても、以前とは変わってしまったのを感じます。
今からはじめよう! 防災対策
小学校の避難訓練は1カ月に1回を目標に
ここ、人と防災未来センターでは、毎日たくさんの方に来館いただいています。
中には、小学校の子どもたちもいます。そのとき、小学校の先生には、「避難訓練は年に1回では不十分、月に1回はしてほしい」とお願いしています。
というのも、2003年7月に起きた宮城県北部の地震では、阪神・淡路大震災と同じ規模だったのに死者はゼロだったということがあります。もちろん、人口の違いもあるのですが、たとえば被害の大きかった宮城県成瀬町では月に2回の避難訓練を行っているんです。こうした日ごろの成果が死者ゼロに繋がったのではないかと思います。
年に1回の訓練では足りない、月の1回の訓練をお願いしています。
家族と避難場所を決めておく、そして実際に歩いてみる
また、学校だけではありません。各ご家庭でも避難訓練について考えておく必要があります。
地震は、いつ何時起こるかわかりませんから、お子さんのいる家庭では子どもとチリチリバラバラになることもあります。そのとき、家族の集合場所を決めていれば安心です。場所は、小学校、中学校のあるところ、どちらでもいいです。
小学生以下のお子さんは、避難場所を頭で教えていても覚えられません。実際に避難場所への道を歩いて覚えておくことが大切です。
実際に歩いてみると、消火栓の設置場所や、電柱の場所などいろんな情報が得られます。こうしたことを事前に知っておくと、避難のときに安心なのです。
ご近所付き合いを大切に
さらに、日ごろから近所の人と交流しておくことも大切です。
阪神・淡路大震災のとき、救助された人の78%が近所の人に助けてもらったといいます。大震災のときは、消防も警察も被災者ですから、助けてもらえないものだと思っておくべきなのです。
とにかく、町内でできることは、町内ですること。日ごろから近所の人と挨拶をしたり、行事に参加して、顔を覚えてもらう・覚えておくことが大事なのです。
防災グッズはまめに交換を
防災グッズは、水、食料(ビスケット・乾パン)、懐中電灯、携帯ラジオ、この4点は絶対に備えておきたいところです。特に、携帯ラジオは毎年電池を取り替えておくのがおすすめです。
毎年、防災グッズをチェックする習慣をつけておくといいでしょう。
ちなみに、防災グッズは1人1セットを持っておくこと。4人家族なら4セット用意しておくべきだと思います。
インタビュー 2004年9月17日 (2022年10月1日 改訂)


