震災を語る 第15回
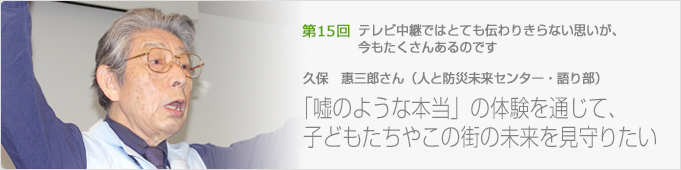
私の体験
震災直後の映像が映し出したもの、映し出せなかったもの

これは私の生まれ育った街・長田が被災した航空写真です。写真を見たイギリスの新聞記者は「これはヒロシマではないか!」と叫びました。原爆が落ちた時のように、この街は一瞬にして壊滅したのです。あの朝、いち早く報道ヘリコプターによって中継されたテレビ映像は、全国の視聴者にとって悪夢のような出来事に見えたに違いありません。しかし、私たちはそれすら見ることができませんでした。地中からの助けを呼ぶ声はヘリコプターの爆音にかき消され、テレビやラジオ、電話などの外界とのコミュニケーション手段も、すべて瓦礫の下に埋もれてしまったのです。
あの時、壊滅した大地に「この下に人が埋まったままです」の立て看板がありました。激しい揺れとともに埋もれてしまった人がいて、それを知らせようと記した人がいて、それを撮影した人がいたのです。埋まってしまった人はどうなったのか? 記した人はどこに行ったのか? 撮影した人は助けを呼んだのか? 現場では、こうした結末のないドラマが静かに進行していました。
「嘘のような本当」の体験を、皆さんに知っていただくために
「人と防災未来センター」へ来館された皆さんに、まずご覧いただくのが阪神・淡路大震災の「体験映像」。大音響とともに足元が揺れ出し、大型の立体マルチスクリーンには家が崩れ、ビルがひしゃげ、駅が裂け、高速道路が倒壊する有り様がリアルに映し出されていきます。再現される映像・音響・照明の効果によって、その恐怖心はピークに達するといわれます。それから、展示室でビデオや写真記録による実際の被害状況を見ていただき、語り部の話を聞いていただくという流れになっています。
センターがオープンした時、お客様に1人の「語り部おじさん」が話し始めました。さぞ大変な苦難話かと思いきや、「情けのうて…情けのうて…」と泣き出し、絶句してしまったのには驚きました。「あの時、どうすることもできなかった自分」を責めているんですね。被災者一人ひとりの魂の奥底に沈んでしまった言葉にならない思いがあることに、私はその時気付かされたのです。
戦災にしても震災にしても、映像の記録というものは見た人々に生々しいショックを与えます。しかし、それはどんなにリアルな映像でも、レンズを通して見る「疑似体験」にすぎません。身体全体で味わった(皮膚感覚のような)阪神・淡路大震災の体験は、それぞれに感じ方は違っても特別なもの。私は「それは、嘘のような本当の体験でした…」と、語り始めるのです。
スローモーションで見た、恐怖の瞬間
あれはお正月の延長、14、15、16日と続く3連休でした。充分すぎるほど飲み食いし、「明日から仕事か」と床に就き、ぐっすり寝込んでいた明け方のことです。ゴーッと地底を這うような音が聞こえたかと思うと、ユサユサユサとゴンドラに乗っているような横揺れがしました。続いて、ガラス食器の割れる音、本が落ちる音、机が滑り出す音…そこへ、ガスの臭いがクンと鼻をつきました。瞬発的に「危ない、止めろ!」と妻に命令。中庭の元栓を閉める姿を見たその時、夜空に白銀色の光がパアーッと広がるのが見えました。途端ドーンと縦揺れがして、私は飛び上がりました。すると、お向かいに建っていたお寺が、ゆったりと音もなく崩れていきました。それはまるで、テレビでお相撲さんがスローモーションで倒れていく姿を見ているよう。しばらくして、白い埃がゆっくりと舞い上がったのが不気味でした。この時、人は恐怖の瞬間には何の感情もなく、時間がゆっくり流れていくように見えるということを知ったのです。
変わり果てた街、92歳になる恩師は大丈夫か?
何時間経ったころでしょうか。私は闇の底からやっと這い出し、玄関口に出ていました。近所の奥様方が寝間着のまま毛布を被ってヒソヒソ話の最中です。「あんたとこ大丈夫?」「私んとこは大丈夫だったけど、向かいのおばあちゃん1階に1人で寝てたでしょう。2階が落ちて死んじゃったの」声を殺しての会話内容は、「向こう3軒両隣死人の山」といった残酷なものでした。
その時急に、子どものころからお世話になっていた幼稚園の先生のことを思い出しました。先生は92歳のひとり暮らし。「大変だ!」と表に飛び出して、驚きました。道路には2階・3階建ての住宅が積み木崩しのように突き刺さっていて、そこにコンクリートの電柱がX字に通せん坊をしています。粉塵が白く立ち込めていて、まるでエイリアンの街のようにひっそりと静まり返っていました。
先生のマンションまでたどり着き、呆然としました。1階が陥没して、なくなっているのです。ガラスを破ってお部屋まで這い上がり「大丈夫ですか!」と怒鳴りますが返事がありません。しかし、ちゃぶ台の上にあったはずの亡き奥様の写真がないのでホッとしました。先生は、生涯の思い出を抱きしめて自力で脱出されたに違いありません。教会学校に飛んで行くと、子ども椅子にただひとり、額から血を垂らしてポツンと座っておられました。妻が1個だけ残っていたオレンジを差し上げ、先生がニコッと笑われたその時、はじめて涙がドワッと出たのです。「人間悲しい時には泣かない。希望を持つよう笑おうとするんだ」戦争に駆り出され多くの戦友を失った先輩の言葉が、改めて思い出された瞬間でした。
「奪い合えば足りぬ。分かち合えば余る」とは、このことです
夜が明け、電気・ガス・水道、すべて無しの生活が始まりました。息を吹き返した被災者たちが、情報と食を求めて学校や公園に集まってきます。真冬の六甲おろしは冷たすぎます。自宅の廃材を集めては燃やして暖を取る…それは自分の脚を食う蛸のような情景でした。センターを訪れた学生さんたちから、「何を食べ、何を飲んでいたのですか?」という質問がよくあります。電気・ガス・水道というライフラインが、すべてダメになった時のことです。1階がすべて陥没してしまった商店街で商品を掘り起こし、「コーラが出てきた。飲まないか?」と分けてくれたお店の方がいました。誰からともなく助け合いが生まれたのです。「家の井戸水は誰でも自由にお使いください」「××小学校で温水シャワーが使えるよ」「○○さん宅で泊めてくれるよ」と、温もりのある声が被災地を通っていました。
そんな時、私よりお年を召されたご夫婦が「おにぎりが1つ余っているから食べないか?」と言ってくれました。余っているはずがないのに、明日からどうするのだろうか? と思った瞬間にふと気が付いたのです。「余っているから、と言わないと受け取らないだろう」そんなご夫婦の思いやりが伝わり、私は遠慮なくいただきました。そのおにぎりを夫婦で2つに分けたら中に小梅が入っていて、その美味しかったこと。満足してお腹もいっぱいになったことが忘れられません。いつ倒壊してもおかしくない我が家へと戻ると、いつでも脱出できるように靴を履いたまま食卓の下に潜り込み、私たち夫婦は抱き合って眠りました。
皆さん、ここに1つのコッペパンがあるとします。これを仲間の誰かが独り占めして食べたって、後ろめたくて少しも美味しくありません。でも、これを100人の友達と人数分に分けあって食べたら…どんなに美味しく、どんなに楽しく賑やかで、満ち足りた思いになることでしょう! 震災現場に立っていた「奪い合えば足りぬ。分かち合えば余る」という格言は、まさにこのことです。こうした気持ちが、人々の中に生まれていたんですね。

「希望色」をした、1万本の菜の花の贈り物
震災の3カ月後、西宮の小学校で卒業式が行われました。いつもと違ったのは、お友達が数十人いなくなっていたこと。その時どうしたことか、千葉県のお百姓さんから1万本の菜の花が送られてきたのです。添えられた手紙には「菜の花は黄色い色。黄色い色は希望の色。希望を持って生きてください」とありました。神戸で被災した子どもたちは「地震にも負けない強い心を持って、亡くなった方々の分も毎日を大切に生きてゆこう」そして「しあわせを運べるように」と、思いを歌にしました。
そんな子どもたちの未来のために、地震を通じて語り合いたい。この街の未来を、将来の若者たちとともに見守りたい。あの日からもう11年が経ちました。「語り部は、私が神様に与えられた天職かな」と思う今日この頃です。
(インタビュー 2006年4月20日)


