震災を語る 第35回
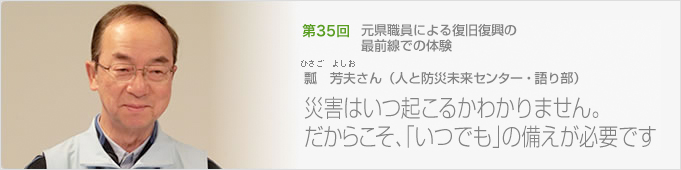
私の体験
人と防災未来センターの「語り部」
私は、平成20年から「語り部ボランティア」をしています。平成7年の震災から何年もの間、
私にとって震災は「語る」どころか「思い出したくもない!」ものでした。しかし、平成20年、長年勤めた兵庫県庁を退職したのを機に、この震災の復興・復旧に携わった体験を「語り継がなければ!」と思うようになりました。
体験したこと、語り継ぎたいこと
私は、神戸市長田区で被災しましたが、幸いにも家族を亡くすことも家を失うこともありませんでした。私の語りは、震災当時勤務していた兵庫県阪神県民局(尼崎市)での、震災の復旧・復興の仕事にかかわった体験談です。
私の手もとに、「阪神の震災3か月記録」と題する手記があります。これは、震災当時勤務していた兵庫県阪神県民局での、震災対策に奔走した日々を日誌風に記録したものです。
この体験は、平常時の役所では考えられない異常で過酷なものでした。事務所の冷たい床の上にダンボールを敷き、数枚の毛布にくるまって、何日も寝泊りしました。
都市のコミュニティの弱さを知った
被災地では都市でも田舎でも、たくさんの高齢者が亡くなりました。倒壊した2階建ての住宅の多くは1階部分が押しつぶされましたが、ほとんどの高齢者は1階に寝ていたからです。
神戸市長田区では921人、震源地の淡路島北淡町では39人が亡くなりましたが、注目したいのは、倒壊家屋の瓦礫の中から救出された人の数です。長田区で救出されたのは391人で、救出率は約30㌫、北淡町で救出されたのは300人で、約90㌫でした。長田区では(都市では)、隣に住んでいる人のことすら知りません。北淡町では(田舎では)、近隣の家や人などの情報はみんなが知り合っています。どの家に高齢者がいるかはもちろん、何時ごろ、どの部屋で寝ているかまで、地域の人たちは知っていました。
高齢者を救出したのは、警察署や消防署や役所の人ではなく、地元の消防団や青年団や近所のみなさんでした。田舎の「ご近所の底力」が、人命救助に発揮されたのです。都市のコミュニティの弱さを知りました。
避難所で人間の生き様を見た
1,000か所を超える避難所の避難者は、ピーク時には30万人を超えました。震災直後の数日間、避難者が求めたものは、ひたすら「生きること」でした。そのためには、命をつなぐ「水と食料」と寒さをしのぐ「毛布」が必要でした。しかし、それらはまったく不十分でした。それでも避難者は、文句をいわず、水も食料も毛布も分け合い、助け合い、励まし合って生きました。
しかし、わずか数日で避難者の要望は変化していきました。「こんな冷たいメシが食えるか!」、「避難所が寒い、狭い!」、「もっと情報をくれ!」、「仮設住宅を早く建てろ!」要求はどんどん大きくなっていきました。際限のない人間の生き様を見た思いでした。>
行政の限界に気づいた
私は、阪神の被災地のうち芦屋市を担当しました。被害は全市域に広がり、まさに壊滅的でした。人口87,000人のうち20,000人が避難所に避難しました。
20,000人の避難者の命を守るために必要な食料「おにぎり」を例にとると、最低でも朝2万個、昼2万個、夜2万個のおにぎりが必要でした。しかし震災直後の数日間は、決まった個数も時間もまったく望めませんでした。
例えば、2万人の避難者に千個のおにぎりしか届かないという事態もありました。こんな場合、役所の仕事の仕方には2つの方法があります。一つは、千個を2万個にきざむ方法、二つ目は2万人の中からワースト千人を選ぶ方法です。
しかし、2万個にきざむための「時間」、ワースト千人を選ぶための「時間」によって、2万人は命を落とします。異常時だからいえることですが、そのときの正しい判断は、「どこでもいいから早く千個を配る」というものでした。そうすれば1,000人の命が救えます。たとえ19,000人が救えなかったとしても。
役所の判断基準である「公平」、「平等」は、平常時のものであること、異常時は「即決」と「重点」という判断基準が求められることを震災対策の中で知りました。
「いつでも」の備えが必要です
もし、この震災が避けられず受入れなければならないとすれば、(変な言い方ですが)最もよい季節、最もよい時刻に発生した地震だったと思います。食料が腐らず日持ちする「冬」、人の動きが最も止まっている「未明」だったからです。もし地震の発生が夏で、昼間だったら、何倍もの死者と負傷者が出ていたでしょう。
災害はいつ起こるかわかりません。東海地震などが近い将来予測されていますが、季節も時刻も正確にはわかりません。だからこそ「いつでも」の備えが必要なのです。


